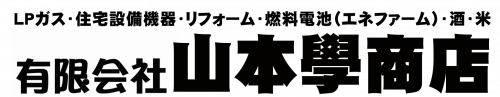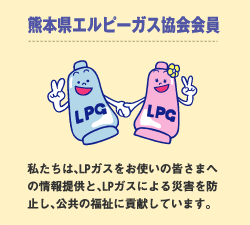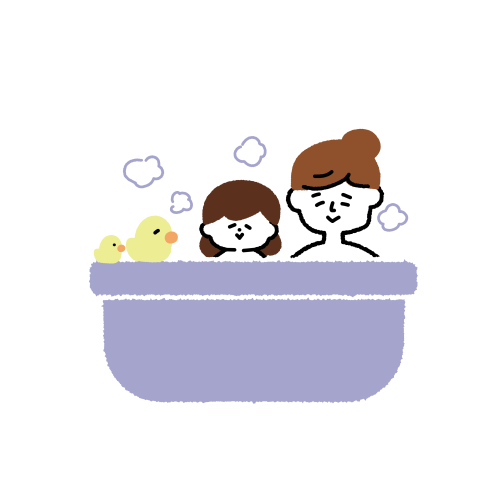ごあいさつ
お知らせ
エネルギー等の価格高騰の影響による支援として、
LPガスを利用しているみなさまを対象に
関係市町村及び熊本県の補助による
支援金(第3弾)申請の受付がスタートしています!
ぜひご活用ください!
支援金額
5,000円(1契約あたり1回限り)
申請期間
令和7年10月14日(火)まで(郵送の場合は当日消印有効)
対象者
●以下の市町村にお住まいの方で、該当の市町村でLPガスをご利用の契約者
※都市ガス契約は対象外です。所得制限はありません。
熊本市、八代市、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、 南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、 山都町、氷川町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、球磨村、あさぎり町
●熊本市内で事業を営む店舗・事業所等
※熊本市以外での事業者(屋号・法人)は対象外です。
申請先
熊本県LPガス支援金事務局
申請方法
申請受付期間中にオンラインでの専用WEBサイトか郵送で申請いただきます。
支援金や申請の詳細については、熊本県LPガス協会の支援金ページをご覧ください。
まだまだ厳しい暑さが続き、残暑のきびしさを感じる9月。それでも季節は少しずつ秋へと移ろい、店頭にはサンマやさつまいも、きのこ、栗など、秋ならではの味覚が並びはじめます。暑さに疲れた体をいたわりながら、旬の食材で食卓に秋の彩りを取り入れてみませんか。ガス火ならではの強い火力や直火調理を活かせば、素材の旨みを引き出し、秋の味わいを一層楽しめます。
ガス火だからこそ味わえる“秋のごちそう”
秋は夏の疲れが出やすい時期ですが、同時に「食欲の秋」といわれる季節でもあります。
サンマ、さつまいも、栗、きのこなど、秋に旬を迎える食材は、栄養豊富で味わい深いものばかり。体調を整えながら、季節を感じられる食卓を彩ってくれます。
こうした旬の食材をよりおいしく仕上げるのに欠かせないのが、ガス火の調理力。直火の強い熱でサンマを焼けば、皮はパリッと香ばしく、中身はふっくらジューシー。煙やニオイを抑えて焼ける魚焼きグリルなら、後片付けも簡単です。きのこは強火で一気に炒めることで水分を飛ばし、香りを立たせるのがポイント。バター醤油やガーリック風味に仕上げれば、ご飯もお酒もすすむ一品になります。
また、秋のスイーツもガス火と相性抜群。さつまいもは弱火でじっくり加熱することで、でんぷんが糖に変わり、甘さが増して“蜜たっぷり”の焼き芋に。電子レンジではなかなか出せない、ほっこりした甘みが引き立ちます。栗は圧力鍋を使えば短時間でホクホクに仕上がり、手軽に栗ご飯や甘露煮が楽しめます。ガス火調理の特長である「強火」と「じっくり弱火」を使い分けることで、秋の味覚が一段と豊かに感じられるでしょう。
旬の食材を「旬のうちに」楽しむことは、栄養面でもメリットが大きいといわれています。季節の食材をガス火でおいしく調理し、心と体を秋のリズムに整えていきましょう。
安心&便利! Siセンサーコンロで広がる調理の楽しみ
「ガス火はおいしいけれど、焦がしてしまいそうで不安」「火加減がむずかしい」と思われる方も少なくありません。
そんな不安を解消してくれるのが、最新のSiセンサーコンロです。
Siセンサーコンロは、鍋底の温度を自動で感知し、必要に応じて火力をコントロールしてくれる優れもの。揚げ物なら設定温度をキープしてカラッと仕上げ、炒め物は高温になりすぎるのを防いでシャキッとした食感を残してくれます。煮物をしていても、吹きこぼれそうになれば火を弱めて調整してくれるので、焦げつきやコンロの汚れを防ぎ、後片付けもラクになります。
さらに便利なのがタイマー機能。グリルで焼くサンマも、セットしておけば焦げる心配なく、ちょうどよい焼き加減に仕上がります。毎日の調理をサポートするこうした機能は、忙しい共働き世帯や子育て世代にこそ心強い存在です。
Siセンサーコンロは安全面でも大きな進化を遂げています。万が一、鍋が空焚き状態になったり、火が消えたりした場合には自動でガスを遮断。小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭でも、安心してガス火を活用できます。
「強火の魅力」と「安心の安全機能」を兼ね備えたSiセンサーコンロがあれば、旬の食材をより気軽に、より安心して楽しむことが可能です。この秋はぜひ、ガス火の良さを再発見しながら、季節のごちそうを食卓に並べてみませんか。

秋の簡単レシピ
さつまいもときのこのバター醤油炒め(2人分)
材料:
さつまいも:1本(200gほど)
しめじ:1/2パック
えのき:1/2パック
バター:10g
醤油:大さじ1
みりん:大さじ1
塩・こしょう:少々
青ねぎ(あれば):適量
作り方:
1,さつまいもは皮付きのままよく洗い、薄めの輪切りにして水にさらします(5分程度)。
2,しめじとえのきは石づきを取り、小房に分けておきます。
3,鍋に水を入れてさつまいもを5分ほど下ゆでして柔らかくしておきます。
4,フライパンにバターを熱し、さつまいもを炒めます。
5,きのこを加えてさらに炒め、しんなりしたら醤油とみりんを回し入れます。
6,味を見て塩・こしょうで整え、仕上げに青ねぎを散らして完成!

夏はなぜ天気が急に変わるの?
梅雨が明ければ、日差しの強い日が増え、気温も一気に上がっていきます。しかし一方で、7月から9月にかけては、実は1年の中でも特に天気が不安定になりやすい時期でもあるのです。
その大きな理由が、「台風」と「大気の不安定化」です。日本近海ではこの時期、南の海上で発生した台風が次々と接近してきます。気象庁の統計によれば、台風の発生数や上陸数が最も多くなるのが、まさに7~9月。
台風がもたらす湿った空気や気圧の変化は、大気の状態を不安定にし、思わぬ形で私たちの生活に影響を与えます。
加えて、近年特に注意が必要とされているのが「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」といった、局地的かつ突発的な激しい雨の増加です。日中の気温上昇によって地表が熱されると、空気中に大量の水蒸気が発生し、それが急激に冷やされることで、急な雷雨を引き起こします。こうした現象は、都市部や山間部、海沿いなど、場所を選ばず発生しやすく、しかも短時間で局地的に大雨を降らせるため、予測が非常に困難です。
朝には晴れていたのに、昼過ぎには突然の豪雨――そんな経験をされた方も少なくないはずです。
そして、こうした天気の急変によって一番困るのが、洗濯物ではないでしょうか。
「せっかく晴れているから外に干したのに、急に降り出した雨で全部びしょ濡れに……」
「室内干しにしても湿気が多くて乾きにくい。生乾きのにおいも気になる……」
「晴れている日や時間を狙って洗濯するのが、毎日の小さなストレスになっている……」
忙しい日々を送る人が多い現代、そういった声は少なくありません。
ガス衣類乾燥機で洗濯のストレスがほぼゼロに!
そんな洗濯ストレスを一気に解消してくれるのが、ガス衣類乾燥機です。
ガス衣類乾燥機の魅力は、なんといってもそのスピード乾燥とふんわり仕上がり。ガスの高火力を活かして、5kgの洗濯物を約52分でしっかり乾燥。電気式の乾燥機と比べても圧倒的な時短が可能で、洗濯から乾燥までを一気に終えられる手軽さが支持されています。
また、約80℃以上の温風で乾かすため、除菌効果が高く、生乾き臭の元となる雑菌の繁殖を抑制。汗をかきやすい夏場の衣類や、部屋干しの臭いに悩まされることもありません。
使ってみると実感できるのが、「天気を気にせず洗濯できる」という圧倒的な安心感です。
乾燥まで簡単・スピーディに済ませられるから、天気予報を確認したり、急な雨にヒヤヒヤする必要はもうありません。
さらに、干す・取り込むといった作業が不要になるため、家事の負担が軽減されるだけでなく、ベランダの使用頻度も減って防犯対策にもつながるといううれしい一面も。
天候が不安定な夏だからこそ、洗濯を“天気に左右されない家事”に変えることが、快適な暮らしの第一歩となります。
この夏は、「ガス衣類乾燥機」で洗濯ストレスのない毎日を始めてみませんか?
台風や集中豪雨のニュースが増えるこの季節。つい先日も、九州南部・北部で相次いで線状降水帯が発生し、各地で観測史上最大級の雨量を記録しています。
6月から7月にかけての日本列島は、まさに災害が集中しやすい季節です。日々の生活に追われるなかで「ちゃんと備えよう」と思っても、つい後回しになってしまう防災対策。だからこそ、気候が荒れやすくなるこの時期に一度、家族の防災対策を見直してみませんか?
防災用品は「日常的に使ってみる」ことが大事!
豪雨による道路の寸断、鉄道や橋の被害、通行止めなどで、スーパーやコンビニに物資が届かなかったり、山間部や川沿いの住宅地では孤立状態になってしまうことも考えられます。
また洪水や土砂災害の危険があると、避難所よりも「自宅で待機」するよう呼びかけられることもあります。
その際、役立つのは自宅での備え。
数日分の食料や水が自宅で利用できる状態であることが極めて重要です。
しかし、防災用品は「あるだけ」では意味がありません。
いざというとき、家族全員が使い方を知っていて、すぐ手が届く場所にあることが重要です。
たとえばカセットコンロは、普段から使って慣れておくことが、防災対策の第一歩。道具の使用期限やボンベの残量なども、定期的なチェックが欠かせません。
チェック項目としては以下のような内容がおすすめです。
・飲料水・非常食の賞味期限確認
・カセットコンロ+ガスボンベの在庫と使用期限
・懐中電灯やラジオの電池チェック
・非常用トイレや簡易寝具の配置場所
・家族の緊急連絡手段(避難先・集合場所の確認)
・高齢者や小さな子のケア用品の備え
せっかく備えていても、使用期限が切れていたり、家族に情報が共有されていなかったことで、いざというときに使えなかった、どこにあるかわからなかった……なんてことも。
それを防ぐためにも、防災用品は家族全員で「日常的に使ってみる」ことが大切! とくに食料は、日々の食事で使いながら消費期限を切らさずに管理する“ローリングストック”がおすすめです。
また最近では、防災チェックリストや備蓄確認アプリなども登場し、家族で共有できるツールも充実してきています。
実は、すごいエネルギー「LPガス」!
LPガスは、電気や都市ガスと比べて、災害時にも使いやすいという特徴があります。その最大の理由は、分散型で、LPガス容器による「個別供給」であること。配管や大規模なインフラに依存しないため、被害を受けにくく、復旧も早いのが強みです。
『自立稼働が可能』
LPガスは、容器(ボンベ)に充てんすることで使用できます。電力などを介さず自立稼働しているため、もし災害で都市ガスや電気の供給が途絶えたときでも、LPガスなら使うことができるのです!
『分散型エネルギー』
LPガスは容器に充てんし、必要な場所に設置できるため「分散型エネルギー」と言われています。容器に充てんすれば簡単に運べることも大きな特徴です。アウトドアでもよく使われています。
『軒下在庫』
家庭用のLPガスは、容器2本セットで設置されるのが基本。そのため、日常から満タンの容器が予備として設置されている状態になっているということになります。“いつもどおり”が備えになっているのですね。
LPガスは、給湯、煮炊き、暖房、発電など行うためのエネルギー源として、避難所となる施設に迅速に設置することができます。これも「分散型」の特性を生かした、LPガスの大きな強みです。
実際に被災地の避難所では、炊き出しや暖房用としてLPガスが多く活用されています。
初夏のきざしが見え始めた今日このごろ、すっかり汗をかく季節となってきました。日中は汗ばむ陽気でも、夜になると意外と体が冷えている……そんな経験はありませんか?
実は、夏こそ「冷え性」が深刻化しやすい季節。
冷房の効いたオフィスや電車、冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎによって、体の深部まで冷えてしまう人が増えています。これが原因で、だるさや肩こり、睡眠の質の低下、自律神経の乱れなど、さまざまな不調を引き起こすこともあります。
夏におすすめの入浴法
“夏の冷え性”対策にこそ効果的かつ簡単に取り入れられるのが、お風呂です。暑さからついシャワーで済ませてしまいがちですが、湯船にしっかり浸かることで、体の芯から温まり、血流や代謝が改善されるだけでなく、心身のリラックスにもつながります。
1. ぬるめのお湯で半身浴(38~40℃)
→ 夏は体温が上がっているように感じますが、内臓や手足が冷えていることが多いもの。熱いお湯では逆にのぼせやすくなるため、ぬるめのお湯で半身浴を。みぞおちあたりまで湯船に浸かり、10〜15分ほどゆっくり温まりましょう。じんわり汗をかく程度が理想的です。
2. 入浴前後に常温の水分補給を
→ 入浴中は意外と汗をかくため、脱水を防ぐためにも水分補給は欠かせません。冷たい飲み物は内臓を冷やしてしまうので、常温の水や白湯がおすすめ。入浴前後にコップ1杯を目安に摂るとよいでしょう。
3. 湯船の中で軽くストレッチ
→ 湯船の中でふくらはぎを揉んだり、足首を回したりするだけでも、血流がぐんとアップします。肩や首を軽く回すのも効果的。体が温まった状態で行うと、筋肉がほぐれやすく、冷えやコリの解消にもつながります。
4. 炭酸ガス系や温感系の入浴剤を活用
→ 夏はさっぱり系の入浴剤を選びがちですが、冷えが気になる方は炭酸ガス系や生姜・トウガラシなどの温感系を選ぶのもおすすめ。血行促進作用があり、湯冷めもしにくくなります。香りのよいものを選べば、リラックス効果もアップ。
5. 入浴後はタオルドライ&保温を意識
→ 湯上がり後、体を冷たい風に当ててしまうと、せっかく温まった体がすぐに冷えてしまいます。濡れた肌はやさしくタオルで拭き取り、薄手のパジャマや羽織りものなどで保温を。特に足元が冷えやすい方は、レッグウォーマーや靴下も活用してみてください。
夏に湯船につかるメリットとは?
・内臓の冷えを改善
冷房や冷たい食事で冷えたお腹まわりをじっくり温めることで、胃腸の働きが整い、便通の改善や食欲の回復にも効果的です。
・自律神経を整える
温熱刺激により副交感神経が優位になり、心が落ち着きます。ストレス軽減や睡眠の質向上にも◎。
・代謝アップ&むくみ予防
血行が良くなることで、代謝が上がり、老廃物の排出もスムーズに。むくみがちな足元のケアにもつながります。
・快眠効果
入浴後に一度体温が上がり、その後自然に下がっていくことで、入眠しやすくなります。寝苦しい夏の夜にもおすすめの習慣です。
暑い季節になると、「お風呂=汗を流すため」としてシャワーで済ませがちですが、体調管理の観点から見ると、湯船に浸かることは夏の冷え対策にとても重要です。
毎日は無理でも、週に数回でもしっかりと湯船に浸かる習慣をつけることで、冷えによる不調を防ぎ、夏を元気に過ごすための基礎が整います。
夏の冷え性は、自分では気づきにくい“隠れ冷え”の場合も多いもの。
ぜひこの機会に、お風呂の時間を見直してみてください。ぬるめのお湯で心身をほぐす習慣が、きっと夏を快適にしてくれるはずです!!